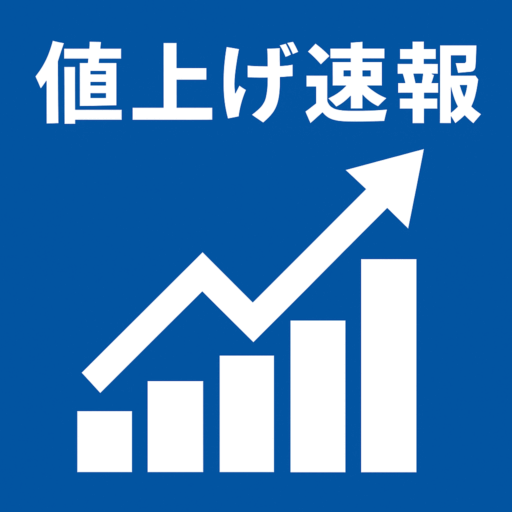以前は「しばらく待っていれば安くなる」と、政府はそう言っていた。しかし、今になっても当時の2倍以上の価格である米5キロの価格が4000円台で維持されている。これは一体なぜなのだろうか?
干ばつの影響
近年、猛暑・長雨・日照不足など異常気象が続き、稲作の生育に影響が出ているようです。先日、とある山形県にあるとうもろこし農家から、懐かしのもちとうもろこしを購入した。しかし、その出来が非常に残念だった。めちゃくちゃ小さくて、もちもち感もない、味も甘さがほとんどなくて、昔の思い出の中のとうもろこしとは程遠いものであった。

今後もこの程度のものしか期待できないのかとメールを送ってみた所、どうやら今年は特に干ばつがひどくて良いとうもろこしが収穫できなかったらしい。それなら売らなきゃいいのに…とは思ったが、売らないと生計を立てられないからしかたなかったのかもしれない。とりあえず、この農家はインスタグラムなどの使い方はうまいけれど、実際に顧客視点に立ててないと思い今後ここで購入することはやめた。
話はずれたが、とうもろこしだけでなくお米にもこのような干ばつの影響があるならば多少は仕方ないかもしれない。
しかし、政府が言っていたのは、「備蓄米があるから」なんとかなるというようなことで、今年の収穫によるお米の量に左右されないはず。
備蓄米はどのように放出されているのか
農林水産省 が発表している「政府備蓄米(=備蓄してあるお米)の放出(=市場に出す)量」のデータがあるようだ。
農林水産省によると政府備蓄米について、適正備蓄水準を概ね 100万トン程度 と定めている。普段は「非常時(大不作・供給不足)に備えて保有」しており、通常時に大量に主食用米として放出するものではないとのこと。しかし、ここ最近の急激な物価高では放出に値するのではないか?とそう思う。
ただ、実際には「お米が市場に放出された」としても、小売の店頭までその米が届けられて、消費者が“安く買える”形で出回っているかどうかが、かなり限定的という報告があるようだ。
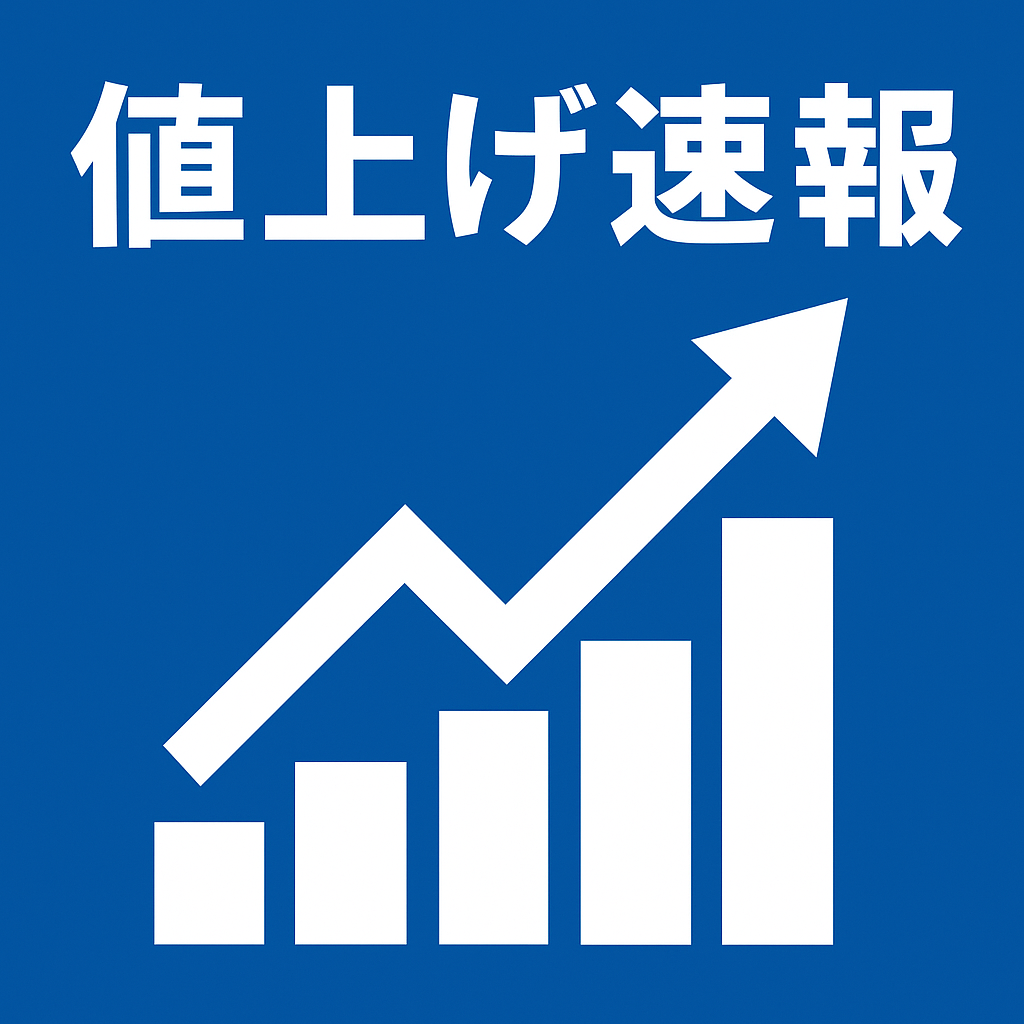 インフレ時代のゆるゆる生活
インフレ時代のゆるゆる生活